こんにちは。ポメラニ・アンパンです。早くも10月になっちゃいました〜!お元気ですか?僕は相変わらずまったり、でも忙しく過ごしています。明日も仕事だぁ・・・。
10月に入って良かったのは、涼しくなった事。9月はほぼ冷房入れていたのに、10月になった途端、冷房必要なくなりました。汗もかく頻度が減って、僕としては過ごしやすい〜!そういう意味でも○○の秋!なんて言うんでしょうね〜。
さて、秋の夜長に最適な、腰を据えてじっくり読める作品無いかな〜とお探しの方に朗報!今日ご紹介するのは今までと毛色が違う作品です。
イスタンブール出身の著者オルハン・パムクの『わたしの名は赤』です。
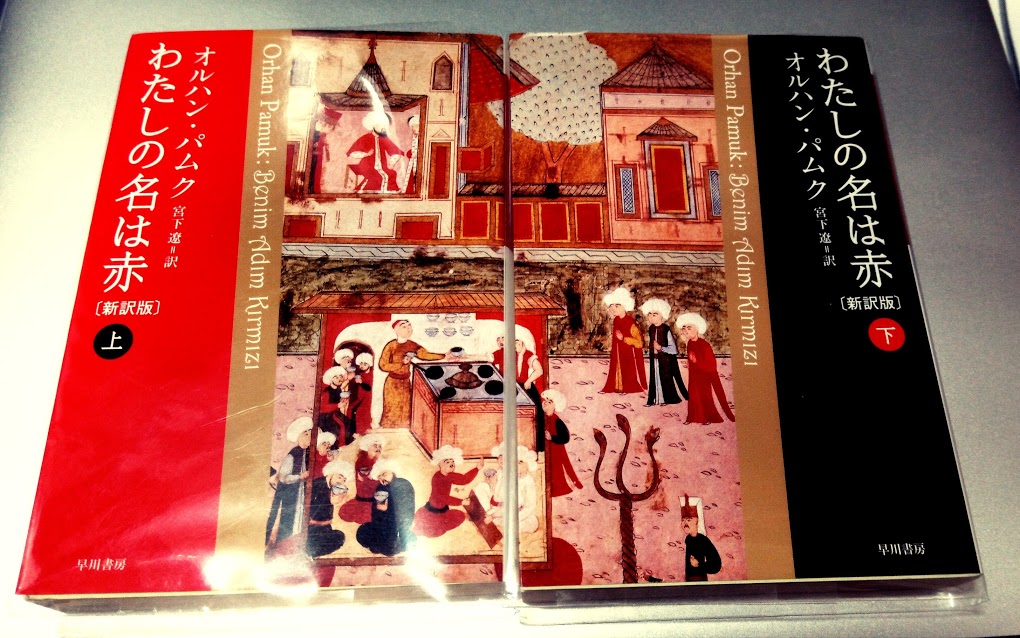
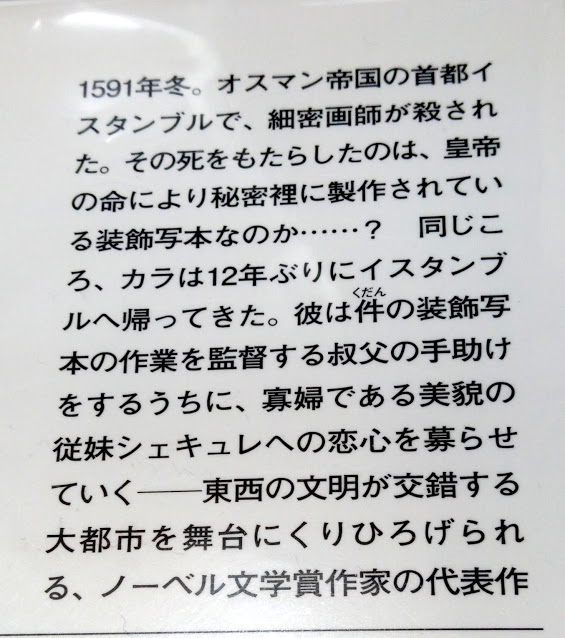
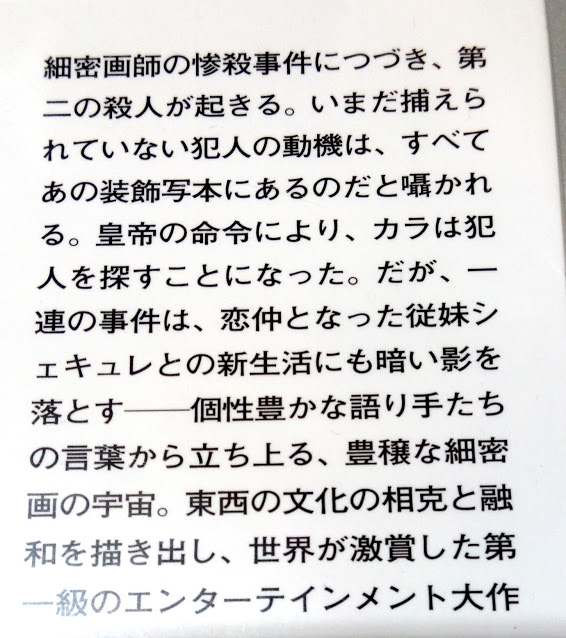
この本を読んだきっかけ
本屋さんで何気なく視界に入ってきたタイトル。手にとって表紙を見て、一旦棚に戻しました。他の棚も眺めて一巡。しかし、どうにも本書のタイトルが忘れられず気になってしまい購入に至りました。まさに、本に呼ばれた感じです。
あらすじ
1591年オスマン帝国の首都イスタンブール。ムラト三世が統治する時代。帝国の黄金期から約半世紀が過ぎ、東のサファヴィー朝ペルシアとは衝突が、西はキリスト教諸国とも対峙が続く状況下で、帝国内にも不穏な空気が漂っていた。
オスマン帝国はイスラム教を礎として成り立つ国家。イスラム教では偶像崇拝は禁止されており、それゆえ絵画もあまり推奨されたものではなかった。しかし、ペルシア由来の絵画は存在し、書物の挿絵として細密画が発展していた。つまり、絵画単体としてはあまり推奨されないが、それゆえ物語の挿絵としての絵画が発展したというわけだ。
本作は、この時代に皇帝から依頼された装飾写本に連なる才あふれる細密画師達、恋を忘れられなかった男、二児の母となった女など、個性豊かな人物達が織りなす歴史ミステリー。
物語はとある細密画師が殺された場面から始まる。時を同じくして、幼い頃に恋した従妹への思いを断ち切れないままだった男が12年ぶりにイスタンブールへ戻ってきた。男は名をカラといった。
カラは、昔世話になったおじ上が寄越した手紙によって呼び戻されたのだ。その手紙曰く、皇帝への装飾写本を作成しており、お前にも手伝って欲しいとの事だった。
おじ上は細密画師であり、昔カラが世話になった人でもあった。カラがまだ6歳ほどの時、気性の荒い父から遠ざけようと、カラの母がおじ上のもとにカラを連れてきた。以後、おじ上はカラを弟子として、細密画の事に限らず様々な事を教えた。
そのおじ上の家で、カラは自分の運命の女性に出会う。おじ上の娘であり、どんな男も恋をせずにはいられない美貌を持つシェキュレだ。例外なくカラもシェキュレに恋をしてしまい、その思いのたけをシェキュレに直接伝えた。しかしそれが過ちだった。おじ上にしてみれば自分の美しい娘に恋をしてしまうのは仕方のない事だと思いつつも、やはりカラを追い出すほか無かったのだ。
こうしてカラはただ絵を描き、学び、美しい娘に恋をする幸せな楽園から去ることになった。カラが去ってから4年後、シェキュレは騎士と結婚し二人の子供を授かっていた。
12年ぶりにイスタンブールへ帰還したカラは、手紙の要請に答えておじ上の家を訪った。一端の男に成長したカラの姿や挙措を、おじ上は気に入った。そして、カラに今手掛けている装飾写本について話した。それは、イスラム教の暦として知られるヒジュラ暦の、一千年を迎える(1591年11月〜1592年10月)までに完成させるよう、皇帝直々に要望された装飾写本だ。

装飾写本:偶像崇拝を禁止するイスラム教では、絵画だけ成立させることは偶像崇拝に近く、推奨されなかった。そこで、文章に添える挿絵として、細密画や装飾写本という形で絵が発展していった。あくまで、文章(物語)ありきの挿絵として、この時代の絵画が発展したようだ。
おじ上曰く、装飾写本の作成には、宮廷の細密画工房のオスマン棟梁の弟子のなかで最も才能ある四人の名人が関わっているとの事。カラには、彼らとのパイプ役をやるようにおじ上が言う。しかし、おじ上が漏らす。彼らのうちの一人が最近姿を表さなくなった。
<優美>は、もしかしたら殺されたのかもしれない、と。
下手人はまだ掴まっていないが、とにかくカラはオスマン棟梁に会いに行くことになった。カラはおじ上の家から追い出された後、ペルシャに渡り位の高い人の書記として働いた。おじ上から教育された細密画の知識を生かし、書家や絵師に渡りをつけ装飾写本を作らせる仕事もしていたのだ。おじ上も、カラのそうした能力に目をつけ、オスマン頭領のもとへ向かわせた。
オスマン棟梁・・・皇帝が住まう宮廷内の工房を統括する偉大なる名人。彼には特に優れた四人の弟子達がいた。彼らはそれぞれに筆名を持つ。<蝶>、<コウノトリ>、<オリーブ>そして<優美>の四人だ。彼らは皇帝からのもう一つの依頼である「祝祭の書」も手掛けている途中だった。その最中、<優美>が姿を消したという。単に行方をくらませたのか、あるいは殺されたのか、この時はまだ誰もその真実を知らなかった。
おじ上が漏らしたように、<優美>が殺されたのは、絵に対する手法の違いによって仲違いし、同じ細密画師に殺された可能性もあると、カラは考えた。そしてオスマン棟梁に「真の絵師と凡庸な絵師を分つものは何か?」と尋ねると、オスマン棟梁はそれを知るために三つの質問をするという。
一つ、様式と署名。自分の筆がこの絵を描いた、この独自の手法は自分のだとわかるようにするか否か。二つ、遥か未来まで時間が進み、作品がバラバラになって散り散りになり様々な人が自分の絵を見たとしたらどう思うか。三つ、盲目であること。盲目になり、暗闇の中で見ることこそ細密画の真髄だそうな。
カラはおじ上が手がける装飾写本の完成を手伝う名目と、<優美>を殺した犯人を探すという難題を抱え、疑念を確かめるべく三人の名人<蝶>、<コウノトリ>、<オリーブ>を尋ね、先の三つの質問をする。
細密画師それぞれが己の信念と考えを持っていて、犯人につながる手がかかりはなかなか掴ませない。また、カラにとって難題はもう一つあった。イスタンブールに帰ってきて、偶然窓を開けたシェキュレの顔を見た途端、恋の炎が再燃した。商売人の女を通じて手紙のやり取りをし、シェキュレにアプローチするカラ。一方、戦場へ行き四年間も夫が戻らない虹の母であるシェキュレは、見目麗しいカラを想っていないわけではない。しかし、彼女には夫の弟であるハサンという男の存在も無視できなかった。
シェキュレはしばらく夫の家で、ハサンとその父と、息子二人と共に同じ家に住んでいた。しかし、シェキュレに想いを募らせたハサンが手を出してきたため実家のおじ上(彼女にとっては父親)の下に戻っていたのだ。
・・・紆余曲折を経て、カラはなんとかシェキュレと結婚する所までこぎつけ、おじ上の家に寝泊りできるようになった。しかし、今度はシェキュレの父であり、カラが将来父と呼ぶはずだったおじ上が何者かに殺された。しかも自宅でだ。
これを機にカラに様々な困難が降りかかる。ハサンのシェキュレに対する横槍、シェキュレの長男に疎まれる、皇帝陛下の命令でオスマン棟梁と共に呼び出され、<優美>の遺体から出てきた絵を手掛かりに下手人を突き止めるように言い渡される(3日以内にできなければ絵師全員が拷問に処される)・・・などの試練がカラを苦しめる。
果たしてカラは犯人を探し出せるのか。
カラとシェキュレに愛は生まれるのか。
装飾写本は果たして完成するのか。
イスラム教の文化で、オスマン帝国という文化と人種と宗教がごた混ぜになったカオスの中で、歴史と芸術にフォーカスしたドラマがここにある。
この作品の要素・成分 (最低値=1 最高値:10)
雰囲気
オスマン帝国、イスラム教、細密画、装飾写本、イスタンブール、スレイモニモスク、金角湾、パシャ、ベフザード、馬、ムラト三世、珈琲店、犬、西欧、イタリア・・・赤。
16世紀のイスタンブールを舞台に、細密画師達の【表現の方法】を題材に展開される壮大なドラマ。当時のトルコだけでなくオスマン帝国周辺諸国状況や、文化の流入、宗教感、人々の暮らしなどが色彩豊かに描かれた作品。
読みやすさ:4 ⭐️⭐️⭐️⭐️
まず、構成が独特。各章のタイトルが「わたしの名はカラ」、「わたしは諸君のおじ上」、「あたしはエステル」など登場人物の一人称代名詞+名前が題されていて、その章ではその人物視点で物語が描かれるのだ。この構造が分かるまでちょっと難儀した。しかし、それが分かると俄然面白くなる。
もう一つ読みづらい部分は、慣れ親しんでいない日本語が唐突に出てくる。その都度Google先生に頼って読み進めたので読書スピードは遅かった。しかし、新たな語彙は増えた。
ワクワク度:7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
最初はどんな物語なのか想像ができなかった。しかし、途中から大筋と目的が分かる。語り部の視点がコロコロ変わるので、殺人を犯した者、殺された者、それを知らずに疑う者、など十人十色の視点が楽しめる。そう、読者はまるで神になったように彼らの行末を見るのだ。
ハラハラ度:7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
皇帝の命令で、宮廷の宝物庫の中で犯人につながる手がかりを探すシーン。あらゆる書物を開いても手がかりがなく、オスマン棟梁は書物を見ることに心を奪われてしまう。3日以内に犯人を特定できなければ拷問されるという状況はなかなかスリリング。
もう一つは、最後に犯人を割り出す場面。
食欲増幅度:1 ⭐️
食事のシーンはあまり描かれていない。
胸キュン:6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
若い頃、互いに同じ棟梁のもとで切磋琢磨し合い、殴られたりした思い出を語る三人の細密画師達。互いに考え方やルーツは違えど、美しい思い出は忘れていない、そんな情景がなんともこの後の展開に切なさを残す。
ページをめくる加速度:4 ⭐️⭐️⭐️⭐️
日本には馴染みの少ない地名、実在の人物などの描写があるため、サッと読むには適さない。腰を据え、じっくり読む方がベターだろう。
希望度:6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
色々なことがあっても人は生きていける、そう思わせてくれる力強さが、この物語の登場人物全員に言える。男も女も、皆何か強いものを持っている。
絶望度:5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
文化の流入によって、それまで大切にされてきた価値観が失われてしまうのは、仕方のない事だとしてもやはり悲壮感がある。現在でもこの時代の装飾写本や挿絵が見られるのだろうか。見られるなら是非見てみたい。
残酷度:4 ⭐️⭐️⭐️⭐️
殺された者は岩で殴りつけられたと語っていた。また、最後の方では乱闘が起き、血が流れる。
恐怖度:5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
「この中に犯人がいる」と言われつつも、誰が犯人かわからない恐怖。あらゆる人物が怪しく見えてくる。
ためになる:7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
トルコ、イスタンブール周辺の地理に少し明るくなる。また、16世紀当時はオスマン帝国という巨大国家があった。その周囲には西欧諸国、ペルシアなどがあり、この時代の歴史にも興味が湧いた。
泣ける:1 ⭐️
正直泣ける描写は少ない。
読後感:7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
「カラ・・・まあ、良かったんちゃうん?」というカラに対する感想と、物語全体のスケールとしては歴史や宗教、文化をも織り込んだ作品だったので、読後感はなんというか、達成感に近いものを感じた。時を置いてまた読みたい。
誰かに語りたい:7 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
舞台とか映画にしたら面白いと思った。ざっくり言ってしまうと殺人事件と恋物語だから。舞台がオスマン帝国ってだけで僕たち日本人からしたら馴染みが少なく、また憧れでもある。
イスタンブールに行きたくなった!
なぞ度:1 ⭐️
全てを読むと、見事に伏線が回収され、残った謎は無かったように思う。
静謐度:1 ⭐️
それぞれの章の人物視点で描かれるので、文体もその登場人物によって変えてある。それゆえ静謐さは感じられないが、筆者・訳者のこだわりが感じられる。
笑える度:3 ⭐️⭐️⭐️
笑えるというより、カラとシェキュレの進展が遅い恋にヤキモキさせられる。
切ない:6 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
栄枯盛衰。強大な国の文化は、他国から奪ってきてものであったり流入してきたものなど、様々。したがって移ろいやすい。この当時栄えた細密画が廃れて人々から忘れられていくような描写は説得力がある分、寂しさと切なさがつのる。
エロス:5 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
最後の倒錯したシェキュレの、カラへの愛し方、接し方。
データ
| タイトル | わたしの名は赤 |
| 原作タイトル | BENIM ADIM KIRMIZI |
| 著者 | オルハン・パムク (Orhan Pamuk) |
| 訳者 | 宮下遼 |
| 発行元 | 早川書房 |
| コード | (上)ISBN978-4-15-120066-3 (下)ISBN978-4-15-120067-0 |
まとめ
読み終わりました〜。本作は、16世紀のトルコ、つまりオスマン帝国の首都イスタンブールを舞台に、当時芸術として確固たる地位を得ていた装飾写本の挿絵にまつわる物語でした。
今までこの地域を舞台にした物語は読んだことがなく、耳慣れない地名や人物に戸惑いながらも、煌びやかで繊細な装飾画とはどんなものか。細密画とはどのようなものかをGoogle検索しながら少しずつ読み進めていけたのは幸せでした。
当時のオスマン帝国は、巻末の訳者解説にもあるように、珈琲店で噺家が、叙事詩を詠う講談師、詩人などが庶民を楽しませるために盛り上がっていたようです。いわゆるバーみたいな感じでしょうか。なので、今僕らが思う喫茶店とは異なり、どちらかというともっと地下的で、ちょっと近寄り難い雰囲気の方が強かったようです。いわゆるシャレオツな雰囲気とは真逆だったとか!歴史の転換点としてまた地理的にも西欧とアジアの中心としてあらゆるものが入り乱れる混沌としたある種世界の中心的な雰囲気すらあったのではないでしょうか。
そうした事を想像しながら本作を読み進めるのはとても楽しい時間でした。Googleマップでイスタンブール周辺を見たりしながら登場人物達がどこを歩き、走り、寒さに凍えたのか。
また、本作には様々な神秘主義団体の跋扈、イスラム教の教義を厳格に守ろうとするが故に過激な行動に出る一派などが出てきます。それらの人々と接触する、接触を避けるなどの知略を巡らせながら、犯人探しと装飾写本を完成に近づけなければならないカラの苦労はどれほどのものだったか、と想像すると目眩がします。
無学ゆえ、歴史や当時の時代背景については詳しく描けませんが、本作を読んでちょっとトルコ周辺に興味を持ちました。本作中何度も引用された「王書」、「ホスローとシーリーン」など、ペルシア文学も機会があったら読みたいと思いました。
本作の主題は、芸術関連の分野には特に強調される「こだわり」、「様式美」、「迎合できる部分とそうでない部分」をきっかけにして人々がそれぞれの思惑に沿って動いています。それまでの様式に則った方法で描かれる細密画と西欧の肖像画のような「絵」単体として成り立ってしまうものとの相克。これを中心に細密画師達が互いに認め合い、嫉妬し合い、友情を振り返りつつも犯人探しをしなければならない局面に追い込まれるところは秀逸でした。
また時間が経ってから読みたい、そんな作品です。良い作品に出会えたぞ〜〜!!
気に入ったフレーズ・名言(抜粋)
こいつらのほとんどは人を殺す機会がなかったというただそれだけで、自分は無垢なのだと信じきっているのだ。
わたしの名は赤(上)p.44
手紙ってのはただ字面ばかりで出来てるんじゃない。本みたいに、その匂いを嗅いで、手で障って、なぞりながら読むもんである。だから、知恵のある者は「読んで見よう」とか「手紙にはなんと言っている?」とか口にするのさ。頭の悪い連中は「なんて書いてあるか読んでみよう」とか、「手紙はなんて書いてる」なんて言うけど、手紙を読むコツってのは、文字ばかりじゃなくてその膳部を読み解くことなんだよ。
エステル
わたしの名は赤(上)p.88
大名人ミラクによれば、盲目は怖れるにあたらず、それは生涯を神の美に捧げた細密画師に、神が最後に与える幸福なのだそうな。
わたしの名は赤(上)p.174
一つの都が持つ知恵とは、そこに住む識者や図書館、あるいは絵師や書家、はたまたメドレセによってではなく、その暗澹たる裏路地で何千年にもわたって密かに行われてきた殺人の多寡によってこそ推し量られるべきだ。
わたしの名は赤(上)p.218
何世紀にもわたって造られて来たこの世のすべては火災や害虫、そして無関心によって滅び去ってゆくのだから。
わたしの名は赤(上)p.361
赤たることは幸いかな!燃え盛るようで力強い。わたしは知っている。みながわたしに目を留めるのを。お前たちがわたしに抗えないのを。
わたしの名は赤(上)p.393
なによりもまず結婚が先決。まずは結婚しましょう。恋は結婚のあとよ。忘れないで、結婚の前に燃え上がった恋心は、それが叶うと消えてしまうの。あとに残るのは空虚で悲惨な焼け跡だけ。もちろん、結婚のあとに芽生えた恋にもいずれ終わりが来るわ。でもその代わりに幸福が残るの。それなのにせっかちなお馬鹿さんたちは、結婚する前から激しく愛し合い、すべての愛情を使い切ってしまう。どうしてかわかる?人生で一番の目的は愛だと勘違いしているからよ。
シェキュレ
わたしの名は赤(上)p.393
実のところ、耳とは人間の欠点そのものだな。誰の耳を取っても同じではないというのに、結局のところ耳でしかないのだから。まさに一つの醜さと言えよう
わたしの名は赤(下)p.112
神よ、天使たちを人の子の前に跪かせることで、彼らに高慢を植えつけたのは、あなたではなかったか?いまや人の子はあなたが天使に教えたその高慢を自ら行っているぞ。人が人にぬかずき、自らをこの世の根本に据えようとしているぞ。
わたしの名は赤(下)p.186
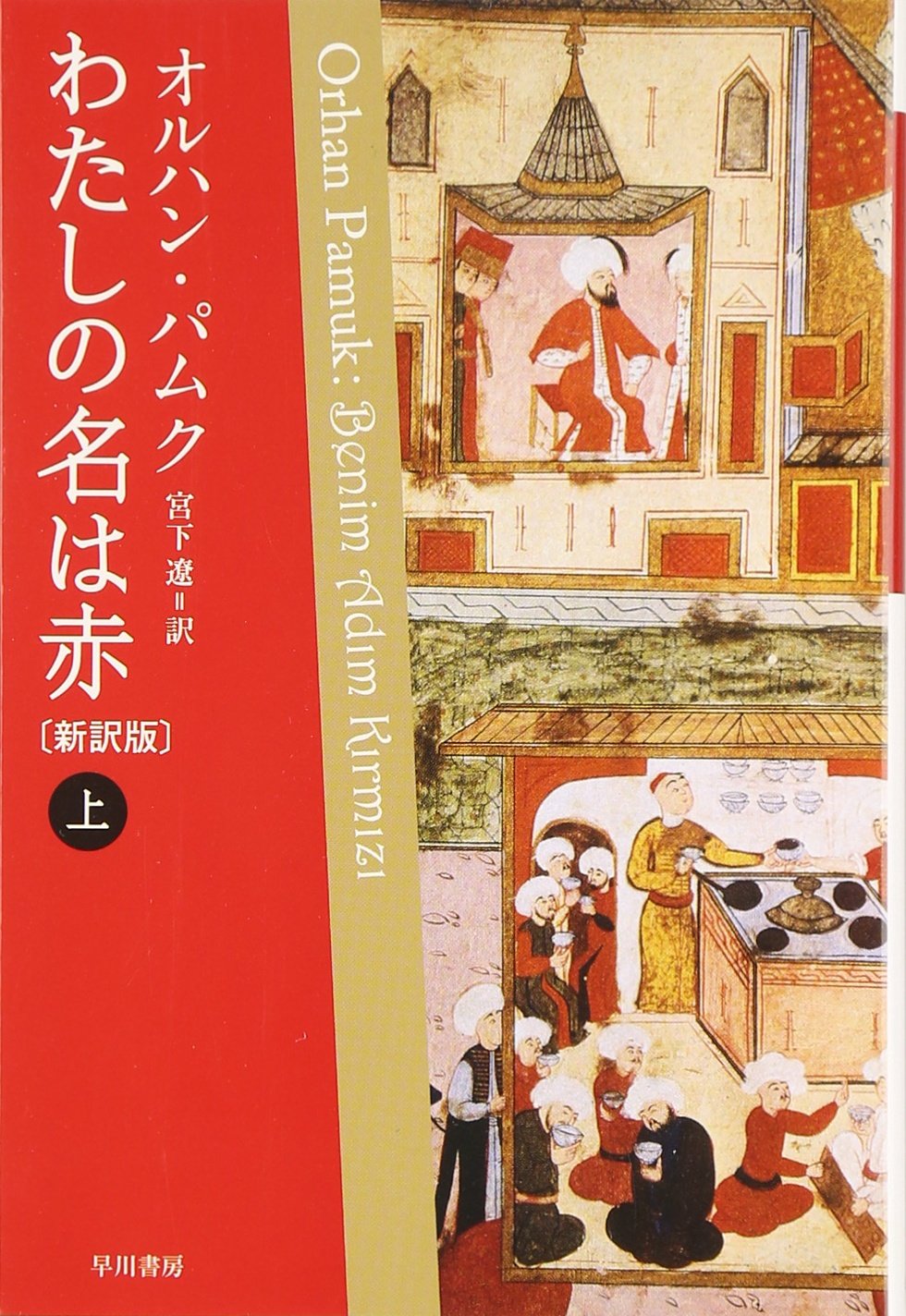
![わたしの名は赤(上)新訳版 (ハヤカワepi文庫) [ オルハン・パムク ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0663/9784151200663.jpg?_ex=128x128)
![わたしの名は赤(下)新訳版 (ハヤカワepi文庫) [ オルハン・パムク ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0670/9784151200670.jpg?_ex=128x128)


コメント